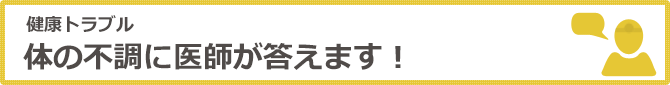最終更新日:2024年5月23日
腎臓と骨の関係
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の働き(GFR)が健康な人の60%未満に低下する(GFRが60未満)か、血尿や蛋白尿が出るといった腎臓の異常が続く病気です。
慢性腎臓病の患者数は約1,330万人とされており、成人の約8人に1人は慢性腎臓病です。
慢性腎臓病が進行すると末期腎不全に至り、透析療法や腎移植が必要となります。
腎臓は血液中の老廃物をろ過し尿として排泄していますが、他にも様々な働きを担っており、実は骨を強くする機能も持っています。
骨の材料となるカルシウムは、腸管で吸収され血液によって骨に運ばれます。
腎臓はカルシウムを腸管で吸収する時に必要となるビタミンDを活性化し、カルシウムを効率よく吸収できるように調整しています。
腎臓の機能が低下すると、食事でカルシウムを摂っても吸収がうまくできなくなります。
また、血液中のカルシウムが不足すると、骨からカルシウムが溶け出て補おうとするので、骨は次第に弱くなってしまいます。
そのため、腎臓の機能が低下すると骨密度が低下し、骨粗しょう症になりやすいことが分かっています。

透析患者さんは骨折しやすい
骨の強さ(骨強度)は骨密度と骨質を合わせたもので、70%が骨密度に、30%が骨質によるものと言われています。
例えば、骨が鉄筋コンクリートだとすると、骨密度がコンクリート、骨質が鉄筋にあたります。
骨粗しょう症を調べるための検査として広く「骨密度検査」が行われています。
しかし骨密度が高くても、骨質が低下していると骨はもろくなっており、骨折を生じる可能性があります。
鉄筋コンクリートの鉄筋が“強い鋼”か“錆びた鉄”かによって、鉄筋コンクリートの強度が異なることをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
現時点で骨質を数値化することはできませんが、加齢だけでなく、腎機能が落ちると骨質が低下することが分かっています。
腎臓の機能が悪くなると、骨密度だけでなく骨質も低下するため、骨が弱くなり骨折しやすくなります。
透析患者さんが大腿骨頸部骨折になるリスクは一般の方と比べて5~6倍といわれています。
骨粗しょう症は、食事療法と運動療法のみで改善するには限界がありますので、薬による治療が必要となってきます。
現在、骨粗しょう症の治療薬が次々に登場し、個々の患者さんの症状や病気の進行度に応じて、選択肢が増えています。
腎機能が低下している方はもちろん、骨粗鬆症のリスクは年齢とともに増加するため、定期的に骨の検査をうけましょう。
将来骨折して寝たきりにならないよう、骨粗しょう症と診断されたら受診するようにしましょう。

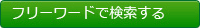
フリーワードを入力
- 美とダイエット|もっとスリムに!美しく!
- 正しいダイエットの方法
- アトピー性皮膚炎って治らないんでしょうか…
- 「ニキビ」「吹き出物」は治療できる病気
- 最近増え続ける脱毛サロン、やっぱり医師にお願いしたほうが効果的?
- 全方位美肌になる、レーザー治療の一問一答
- 新型コロナウイルス関連情報
- 新型コロナウイルス感染症の塩野義製薬の治療薬について
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)③ 検査その2
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)② 検査その1
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)① 概論と症状
- 甲状腺疾患を有する患者様の新型コロナ(COVID-19)ワクチン接種